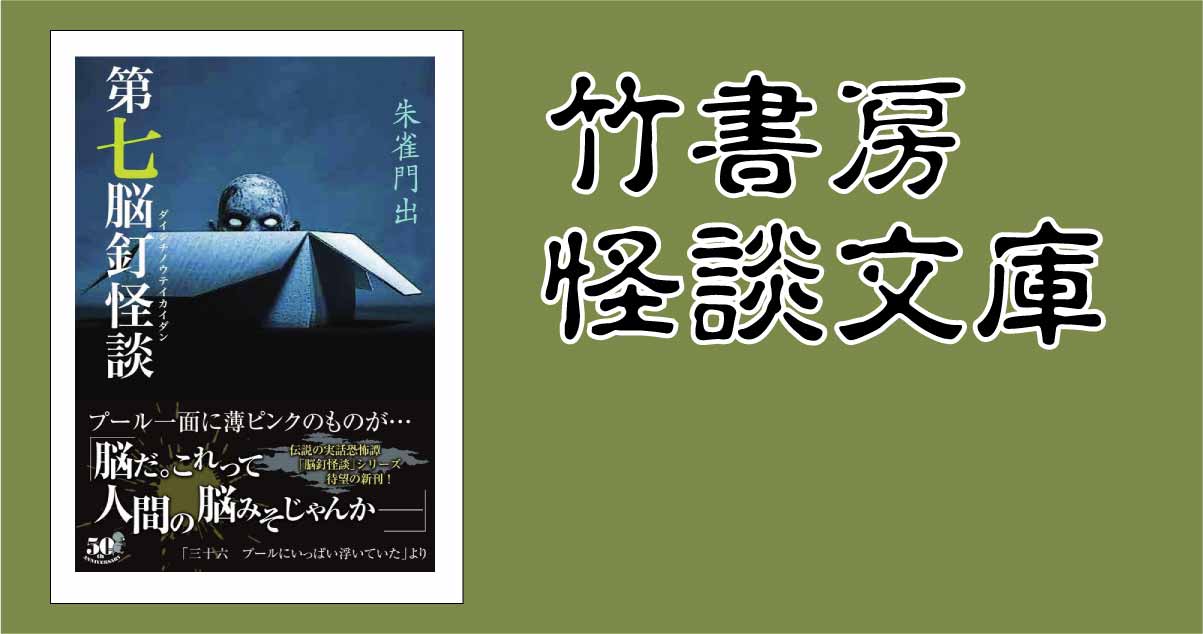朱雀門出:著 竹書房怪談文庫
2022年7月6日 初版第一刷発行
全体評
今まで30年ほど相当数の実話怪談本を読み漁ってきたが、最も特異な怪談作家は誰かと言えば、間違いなく三指に入るのが朱雀門出である。
とにかく集まってきた怪異が尋常ではない。いわゆる《不思議系》の実話怪談の類い希なる書き手なのだが、その奇妙な怪異はまさに「シュール」とか「ナンセンス」という言葉が近いと感じる。あり得ないものがあり得ないところにある、予測不能な現象が唐突に目の前に繰り広げられる、脈絡のない出来事が当たり前のように繋がっていくなど、読み手の常識をさもありなんといった顔で飄然とひっくり返してみせる怪異である。印象としては、恐怖感や気味の悪さよりも先に、口をあんぐりと開けたまま呆然と結末を読み終えるイメージである。恐怖の感情が我々の知っているものとは異質である未知の存在に抱く感情であるならば、その異質が度を超してしまったという表現しかしようがないのかもしれない。もっと個人的な体験で言うと、思わず声を出して笑ってしまった後に、つい辺りを見回してしまうような作品すらある。
そしてさらに他の怪談作家と一線を画すのが、その文体や構成である。
多くの不思議系実話怪談の使い手は、どちらかと言うと、小気味よい文体で怪異の正体を読み手の前にごっそり投げ出して見せつけて驚かせる印象が強い。それに対して朱雀門怪談の文体はあまり小気味よくない。具体的に言うと、接続詞や接続助詞の使用頻度が高さである。接続助詞を一文中に多用して、ズルズルと長く引っ張られているような文が一定頻度で入ってくる。あるいは接続詞を多用して、微に入り細に入り説明・描写や検証・考察が補足的に積み重ねられ、話が進められていく。正直、他の実話怪談作家にはあまりないタイプのスタイルである。
しかし面白いことに、この異質の文体も「シュール」で「ナンセンス」な怪異と相性が良いと感じるところが大きい。喩えるならば、無声映画のスラップスティック・コメディがあたかも無表情でくそ真面目に見える喜劇役者によって演じられるような印象かもしれない。ああでもないこうでもないと色々と言を尽くして言えば言うほど、どんどんと不可解さを増していく印象なのである。
ただこうして言葉を積み重ねていくスタイルなのだが、読んでいる間はあまり厚ぼったいとは感じないし、くどいとも思わない。むしろ何となくゆったりとリズムが取られて、それに合わせて読んでいる感じがする。このあたりは、単純にだらだらと作者が無意味に言葉を重ねているのではなく、ある種言葉のリズムで不思議の世界に誘い込む雰囲気を作っているような印象すら覚える。それ故に個人的には、状況説明や考察の補足的な表記というよりも、あまりにも不思議な世界観を醸し出すために配置された魔術のような仕掛けに思うところである。
そして実際に、このような表記を他の系統の実話怪談に施した場合、やはり作品そのものを壊しかねないとの見解に落ち着く。例えば怪異の因果関係が明確な作品であれば、おそらく冗長すぎて読み手の興味を停滞させ妨げる危険があるだろう。また怪異を通して人を語る種の怪談であれば、読み手の想像力を削り取って白けさせるのがオチであろう。いずれにせよ実話怪談の王道とも言うべき、怪異の醍醐味を殺しかねない書き方になってしまうだろう。しかし逆説的に考えれば、この特異なスタイルを飄々と展開させ怪談として成立させていく朱雀門怪談はそれだけ異色であり、特異な立ち位置にある怪異譚であることが分かるはずである。

各作品について
ネタバレがあります。ご注意ください。
チョキとグーでヤミクラさん
正直言って何が何やらさっぱり分からないが、とにかくとんでもなく気味の悪い怪異譚である。
まずタイトルにある“チョキとグーでヤミクラさん”なる呪文のような言葉が怪異の核となるのだが、それが何を意味しているのか、またその出処来歴を想起させるものや結果として何が起こったのか、全く手掛かりすらなく不明のまま残る。さらにこの訳の分からない言葉を面と向かって言い放つ謎の人物は何者なのか、もっと言えば妹の失踪や烏の大量死とどう関係があるのかないのか。それどころか“チョキとグーでヤミクラさん”を見ることになったDVDそのものが一体何なのかさっぱり見当がつかない。ありとあらゆる怪の事象が関係ありそうで上手く繋がらないもどかしさにのたうち回りながら、その気持ちの悪い状況が進展していく様子を眺めるしかない。
ここまで次々と得体の知れない怪異が続きながらその本質すら全く読み切れない作品は、そうそうお目に掛かることはない。勿論この怪異は精神状態がおかしい人間が見た幻覚でもなく、体験者自身の証言に破綻というものを感じることもない。まさに《不思議》を通り越して、ちゃんと正確に自分が内容を把握できているのか確かめたくなる衝動を覚えてしまった。
おそらく下手な書き方・構成で書き進めていけば、正確に事実を書き記しているにも拘わらず、自然に破綻した内容になっていったであろう。ある意味、朱雀門氏の怪談の真骨頂とも言うべき作品である。
蟒に出遭った話
2つの怪異がコンビレーションされて、相乗効果的にさらに強烈な不思議を見せる好例である。朱雀門氏の怪談ではこういう怪に怪が被さっていく展開も結構よく見るパターンである。その中でもこの蛇にまつわる怪異は、訳の分からない怪異が続くパターンとは逆に、しっかりと前半と後半の怪異の因果が噛み合うことで、レアな内容になっている。前半の蟒に遭うだけ、後半の蛇が喋ったり潰れたりするだけでは怪異としてはさほどインパクトはなかっただろう。
そしてこれもまた朱雀門氏の怪談の特徴の1つだが、展開が突如急変し、猛烈な温度差を生み出すことで生じる怪異というのがある。独特のテンポで軽めの怪異が続いて何となくのほほんとした雰囲気を出しながら(本作では蟒遭遇から青大将のセリフあたりまで)、突如そこから突き放したようなパサパサで冷淡な怪異の雰囲気に豹変する(本作では蛇が潰され全滅から蛇に全く興味を失うところまで)。しかもそれが明らかなギアチェンジをすることなく、同じ力の入れ具合で書かれるように見えるので、気付くと奈落の底に落とされていることがある。これも特徴的な文体スタイルの1つである。
ケンケンする子
この作品も訳が分からない内容なのだが、起こっている怪異に掴みどころがないのではなく、むしろ複数の解釈を施すことが出来て、しかもそれが全て怪異としてあり得るように思えるという、非常に興味深い内容である。
夜中にケンケンしていた子は生身の人間なのか、あるいは幽霊なのか。生身の人間ならば、再度保護した子はドッペルゲンガーだったのか、しかし長らく母親一人で暮らしているという証言をどう解釈すべきなのか。逆に幽霊であれば、子供に対する母親の対応が不自然ではないか、また再度保護した子の存在をどう解釈すべきなのか。とにかく心霊的な知識を総動員してもどうしても完全に納得のいく解釈が得られないほど、奇妙な怪異なのである。
その他には
「靴づくし」(こういう異界を書かせると、一番異界っぽく見える書き方になる)
「掘り当てた太歳のこと」(本当にいたんだ……)
「絶望→希望寺院」(人怖なのか心霊なのかすら曖昧な怪異)
「阿修羅と蜥蜴人」(他の怪談作家が書いたら、おそらく与太話になってしまうのだが)
「赤い風船の少女」(プチ異界譚というか、時空の歪みの怪異として出色)
「コウモリごっこ」(シチュエーションの異様さは群を抜く。そして結末でさらに驚愕)
「プールの水は血」(こじつけと言えばそれまでだが、否定できない薄気味悪さが残る)
「怖い卵を産む」(これもかなり恐怖譚だが、何故か卵の存在でシュールになる)
「インプラントを取り出す話」(内容的にはUFO怪談なのだが、わけの分からなさが半端ない)
あたりが印象に残った。並の怪談ではないことだけは間違いない。