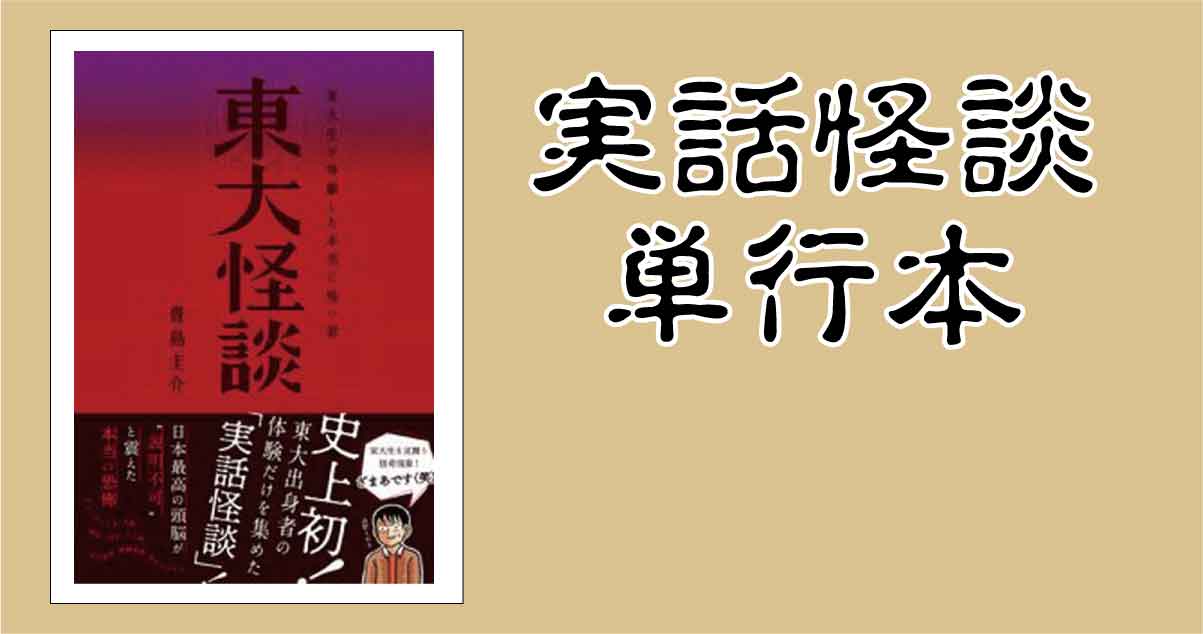豊島圭介 著 サイゾー
2022年3月26日 初版第一刷発行
全体評
怪談作品の一つの潮流として【怪を通して人を語る】というものがある。
怪談と言えば、読者に恐怖や負の感情を抱かせる具体的な怪異をこれでもかと書き連ねていくスタイルが主流であるのは間違いないが、それと同じように、登場人物(実話怪談で言えば体験者やその関係者)に重点を置き、あり得べからざる怪異という特殊な状況に置かれたその人たちの心の機微を丁寧にたどっていくスタイルである。この『東大怪談』は、この【怪を通じて人を語る】実話怪談の典型的な作品となっている。
まず書名のインパクトが相当強い。「東大」と「怪談」をくっつけるという、ある意味荒技っぽいタイトルであるが、見た瞬間に何かわくわくさせるものを感じる。おそらく出身大学で括られた商業誌怪談本は初めてではないだろうか。そういう部分も含めて、期待は大きかった。
その内容であるが、11人の東大出身者(厳密に言うと、中退者や院からの入学者も含まれる)の46の話が収められている。だがその過半は、残念ながら「実話怪談」としては【?】をつけなければならない次元のものであった。もう少し具体的に言うと、「実話怪談」として成立させるための重要な要件を満たさない怪異が非常に多かったわけである。まずこの点を突っ込んでから、評価すべき点を上げていきたい。
認知はあくまで主観であること
あるものを見て、それが面白いか面白くないかを判断する基準が“主観”であることは言うまでもない。実は同じように、あるものを見て、それがAというものであるか、Bというものであるかを判断する基準にも“主観”が入ってくる。特にそれが一般的に認知されていない未知のものであればあるほど、判断基準は“主観”に頼る。
この考えに従えば、怪異の体験は大多数の人にとっては未知のものであるが故に、あくまでその認知は基本的に“主観”の産物となる。たとえ本当に自分自身の目で幽霊を見て「本当にあったんだ!」と主張したところで、結局それだけではただの与太話で片付けられてしまう。だからこそ「実話怪談」を書くに当たって、ある意味絶対的な要件として“客観”的なエビデンスが求められる。例えば、霊が出現した痕跡、複数の人間による証言、時間や場所などの具体的な明示、著名人という担保などが、怪異を語る場合に必要なのである。
ところが『東大怪談』に登場する体験談の多くは、その“客観”を担保するに足るだけの内容が薄い作品がかなりの数ある。もっとはっきり言ってしまうと「勘違いだろ」とか「思い込みが激しいな」という印象が真っ先に出てくるものが結構多い。そして結局読み返しても怪異の“客観”性を裏付けるエビデンスを見つけられないままで終わってしまう。
それ故に“東大”と冠したタイトルを見て、とんでもなく恐ろしい最高レベルの怪異が繰り広げられると思って読むと、その分だけとんでもない肩すかしを喰らわされる。しかも登場する怪異の現象そのものも、正直それほどインパクトのあるものはない。『東大怪談』というタイトルであるが、怪談のレベルが“東大”であるわけがなく、あくまで体験者が“東大”なだけなのであることを、ゆめゆめ忘れてはならない。
主観は人を語らしむ業
では、この『東大怪談』という作品は面白くないのかと問われると、むしろ変に面白いという感想しかない。その面白さは「何故体験者たちは、この現象を怪異と認識したのか」に尽きると思う。それ故に、本来であれば客観的なエビデンスがないという理由で実話怪談として成立不能ではないかと考えてしまうエピソードほど興味深く、そして堪能した。
体験者たちは、現象を怪異と認知するにあたって、理路整然とあるいは確信を持って持論の展開をおこなっていく。言い換えると、普通の怪談本であれば「うわぁ!」とか「あっ……!」というリアクションで終わる部分を滔々と説明、しかもこれが偏差値70の凄味というか実にユニークなのである。読んでいて凄く明晰な思考だなと思う反面、少々紙一重に近い部分も感じる。そしてまたその怪異が一過的な体験ではなく、自身の人間性そのものと密接に関連付いているなと思わせる部分が多分にある。言い方は変だか、この人たちはこういうことを普段から考えて生きているのだろうなと思うに至る内容なのである。まさに【怪を通じて人を語る】作品なのである。
作品の配列を見ると、客観的なエビデンスの面で弱い体験談が後半に集まり、またそれに比例して独特の持論を展開する体験者の色合いが濃くなっており、間違いなく著者の意図は【怪を通じて人を語る】ところにあったのだと思う。
著者は前書きの部分で“自意識”という言葉をキーワードとして上げているが、体験者の多くがこの“自意識”を怪異の客観性の担保としている、要するに己の優秀さを鼻にかけた、独り善がりな解釈という意味ではなく、怪異とは元来個人の主観に立脚して発生し語られるものであることを、この1冊を通して暗に示そうとしているような気もする。根源的な部分において、怪異とはそれの体験者にとって「あったること」であり、それ故にその「あったること」を語ることは、即ちその人の格律や生き様そのものを語ることに繋がるのである。
この本では、上のような視点を強調するかのように、各体験者のプロフィールと言うべきものを前面に押し出してくる。各体験者のまとめとして、著者のコメントである「東大ポイント」や体験者のバックボーンを示すための「『東大怪談』アンケート」は、この本のコンセプトを見事に補強してくれていると感じる。また各エピソードを説明的な文章にせず、体験者の語り口調のままで書き起こしている点にも、体験者のパーソナリティーを前面に押し出すことを相当意識している印象を持った。
フランクでざっくりした作りに見えるが、やはり『東大怪談』は奥が深いと感じ入った次第である。

各作品について
ネタバレがあります。ご注意ください。
全体評で展開した“主観の展開”に関して特筆すべき話
第七話
いきなり“禁じ手”である。いわゆる精神病の病歴のある人の怪異体験は、おそらく普通の怪談作家であれば、その体験そのものの客観性に疑いを持って敬遠するのが大概である。しかしそれを堂々と明らかにして、尚且つ、整合性を維持しながら怪異を語るという、まさに反則に近い禁じ手である。最終的にこれらのエピソードを怪異としてギリギリで成立させているのが“東大”というネームバリューであることも何となく透けて見えてくるわけで、ある意味異質の怪談話である。
第八話
これもおそらく怪異ではなく、体験者が語っているように、認知症の女性と偶然思わぬ場所で出会っただけの体験だと考えるのが妥当である。しかし敢えて体験者自身がこの出来事を“怪”と認知し、そこから論を進めていく流れは、怪異の認知とは詰まるところ主観の産物であること、そしてある現象を怪異と認知することが体験者自身の格律に繋がっていることを明瞭に示している。著者がこの話を“東大怪談”と断言している点が実に印象的であった。
第十話
一番多くの体験談を提供された方だが、特に最終エピソードで「思い込みが強いなぁ」と感じてしまうところがあった(私自身も全く同じように、他者とは異なる記憶を有しているが、自分の勘違いだろうで済ましているせいもある)。ただそれは強力な格律があっての結論であり、その観念のよどみない部分に“東大怪談”というものを感じてしまう。単に自分の体験したことを無批判に垂れ流して主張しているわけではなく、そのあたりは与太話として聞き流すレベルとは明らかに異なる。
しかしながらこのエピソードもおそらく客観的なエビデンスが本人の記憶だけに留まっているので、純然たる「実話怪談」としては一歩引いて眺めるしかない話という印象である。個人が一人でいる時に霊を目撃したという次元ではなく、社会的に公人とみなされる有名人に関わる話なので、個人の記憶だけで結論付けるには難しいと思うところである。